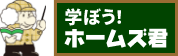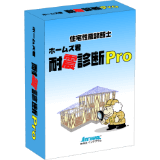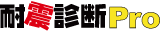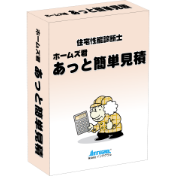震度階級解説表
震度は、地震動の強さの程度を表すもので、震度計を用いて観測します。
この「気象庁震度階級関連解説表」は、ある震度が観測された場合、その周辺で実際にどのような現象や被害が発生するかを示すものです。
※2009年3月31日に、震度階級が更新されました。
人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況
| 計測 震度 |
震度 階級 |
人の体感・行動 | 木造建物(住宅)の状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 耐震性が高い | 耐震性が低い | |||
| 0.5未満 | 0 | 人は揺れを感じないが、地震計には記録される。 | ||
| 0.5以上 1.5未満 |
1 | 屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる。 | ||
| 1.5以上 2.5未満 |
2 | 屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じる。 眠っている人の中には、目を覚ます人もいる。 |
||
| 2.5以上 3.5未満 |
3 | 屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。歩いている人の中には、揺れを感じる人もいる。眠っている人の大半が、目を覚ます。 | ||
| 3.5以上 4.5未満 |
4 | ほとんどの人が驚く。歩いている人のほとんどが、揺れを感じる。眠っている人のほとんどが、目を覚ます。 | ||
| 4.5以上 5.0未満 |
5弱 | 大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。 | 壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがある。 | |
| 5.0以上 5.5未満 |
5強 | 大半の人が、物につかまらないと歩くことが難しいなど、行動に支障を感じる。 | 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 | |
| 5.5以上 6.0未満 |
6弱 | 立っていることが困難になる。 | 壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがある。 | 壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。壁などに大きなひび割れ・亀裂が入ることがある。瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。倒れるものもある。 |
| 6.0以上 6.5未満 |
6強 | 立っていることができず、はわないと動くことができない。 揺れにほんろうされ、動くこともできず、飛ばされることもある。 |
壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 | 壁などに大きなひび割れ・亀裂が入るものが多くなる。傾くものや、倒れるものが多くなる。 |
| 6.5以上 | 7 | 壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。まれに傾くことがある。 | 傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。 | |
|
(注1)
|
木造建物(住宅)の耐震性により2つに区分けした。耐震性は、建築年代の新しいものほど高い傾向があり、概ね昭和56年(1981年)以前は耐震性が低く、昭和57年(1982年)以降には耐震性が高い傾向がある。しかし、構法の違いや壁の配置などにより耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。 |
|
(注2)
|
この表における木造の壁のひび割れ、亀裂、損壊は、土壁(割り竹下地)、モルタル仕上壁(ラス、金網下地を含む)を想定している。下地の弱い壁は、建物の変形が少ない状況でも、モルタル等が剥離し、落下しやすくなる。 |
|
(注3)
|
木造建物の被害は、地震の際の地震動の周期や継続時間によって異なる。平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震のように、震度に比べ建物被害が少ない事例もある。 |
鉄筋コンクリート造建物の状況
| 震度 階級 |
鉄筋コンクリート造建物 | |
|---|---|---|
| 耐震性が高い | 耐震性が低い | |
| 5強 | 壁、梁(はり)、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が入ることがある。 | |
| 6弱 | 壁、梁(はり)、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が入ることがある。 | 壁、梁(はり)、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が多くなる。 |
| 6強 | 壁、梁(はり)、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が多くなる。 | 壁、梁(はり)、柱などの部材に、斜めやX 状のひび割れ・亀裂がみられることがある。 1階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものがある。 |
| 7 | 壁、梁(はり)、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がさらに多くなる。 1 階あるいは中間階が変形し、まれに傾くものがある。 |
壁、梁(はり)、柱などの部材に、斜めやX 状のひび割れ・亀裂が多くなる。 1階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものが多くなる。 |
|
(注1)
|
鉄筋コンクリート造建物では、建築年代の新しいものほど耐震性が高い傾向があり、概ね昭和56年(1981年)以前は耐震性が低く、昭和57年(1982年)以降は耐震性が高い傾向がある。しかし、構造形式や平面的、立面的な耐震壁の配置により耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。 |
|
(注2)
|
鉄筋コンクリート造建物は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも、軽微なひび割れがみられることがある。 |
地盤・斜面等の状況
| 震度 階級 |
耐震性が高い | 耐震性が低い |
|---|---|---|
| 5弱 | 亀裂※1や液状化※2が生じることがある。 | 落石やがけ崩れが発生することがある。 |
|
5強
|
||
|
6弱
|
地割れが生じることがある。 | がけ崩れや地すべりが発生することがある。 |
| 6強 | 大きな地割れが生じることがある。 | がけ崩れが多発し、大規模な地すべりや山体の崩壊が 発生することがある※3。 |
| 7 |
|
(注1)
|
亀裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを亀裂として表記している。 |
|
(注2)
|
地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進行すると、地面からの泥水の噴出や地盤沈下が起こり、堤防や岸壁が壊れる、下水管やマンホールが浮き上がる、建物の土台が傾いたり壊れたりするなどの被害が発生することがある。 |
|
(注3)
|
大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成されることがある。また、大量の崩壊土砂が土石流化することもある。 |
ライフライン・インフラ等への影響
| ガス供給の停止 | 安全装置のあるガスメーター(マイコンメーター)では震度5弱程度以上の揺れで遮断装置が作動し、ガスの供給を停止する。さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供給が止まることがある※。 |
|---|---|
| 断水、停電の発生 | 震度5弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある※。 |
| 鉄道の停止、 高速道路の規制等 |
震度4程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、運転見合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる。(安全確認のための基準は、事業者や地域によって異なる。) |
| 電話等通信の障害 | 地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネット等による安否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにくい状況(ふくそう)が起こることがある。そのための対策として、震度6弱程度以上の揺れがあった地震などの災害の発生時に、通信事業者により災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などの提供が行われる。 |
| エレベーターの停止 | 地震管制装置付きのエレベーターは、震度5弱程度以上の揺れがあった場合、安全のため自動停止する。運転再開には、安全確認などのため、時間がかかることがある。 |
※ 震度6強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給が停止することがある。
大規模構造物への影響
| 長周期地震動※による 超高層ビルの揺れ |
超高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コンクリート造建物に比べて地震時 に作用する力が相対的に小さくなる性質を持っている。しかし、長周期地震動に対しては、ゆっく りとした揺れが長く続き、揺れが大きい場合には、固定の弱いOA機器などが大きく移動し、人も 固定しているものにつかまらないと、同じ場所にいられない状況となる可能性がある。 |
|---|---|
| 石油タンクのスロッシング | 長周期地震動により石油タンクのスロッシング(タンク内溶液の液面が大きく揺れる現象)が発生し、石油がタンクから溢れ出たり、火災などが発生したりすることがある。 |
| 大規模空間を有する 施設の天井等の破損、脱落 |
体育館、屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁など構造自体に大きな被害を生じない程度の地震動でも、天井等が大きく揺れたりして、破損、脱落することがある。 |
※ 規模の大きな地震が発生した場合、長周期の地震波が発生し、震源から離れた遠方まで到達して、平野部では地盤の固有周期に応じて長周期の地震波が増幅され、継続時間も長くなることがある。
留意事項
気象庁発表の震度について
気象庁が発表している震度は、原則として地表や低層建物の一階に設置した震度計による観測値です。この資料は、ある震度が観測された場合、その周辺で実際にどのような現象や被害が発生するかを示すもので、それぞれの震度に記述される現象から震度が決定されるものではありません。
地震動について
地震動は、地盤や地形に大きく影響されます。震度は震度計が置かれている地点での観測値であり、同じ市町村であっても場所によって震度が異なることがあります。また、中高層建物の上層階では一般に地表より揺れが強くなるなど、同じ建物の中でも、階や場所によって揺れの強さが異なります。
震度に対する被害例について
本ページで示している被害例は、ある震度が観測された際に発生する被害の中で、比較的多く見られるものを記述しており、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあります。また、それぞれの震度階級で示されている全ての現象が発生するわけではありません。
また、震度が同じであっても、地震動の振幅(揺れの大きさ)、周期(揺れが繰り返す時の1回あたりの時間の長さ)及び継続時間などの違いや、対象となる建物や構造物の状態、地盤の状況により被害は異なります。
震度階級について
1996年(平成8)年10月1日から、気象庁震度階級の改定により震度5及び6にそれぞれ強と弱を設け、10階級となりました。